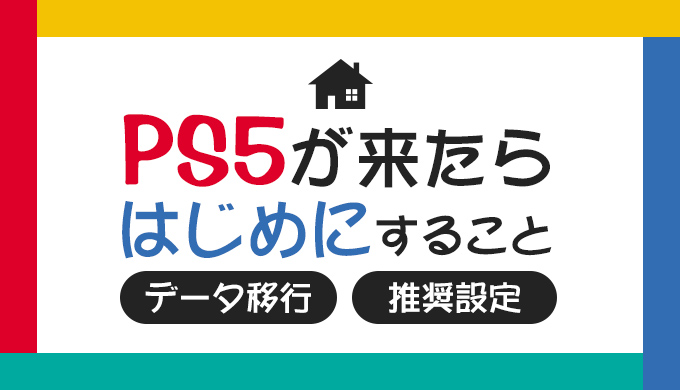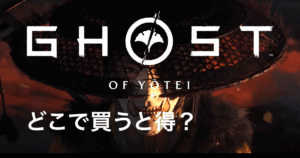『デス・ストランディング2』は、私が言うまでもなく人気な作品で、「神ゲー」「唯一無二」といった高評価の声も多く見かけます。(発売前は地上波のニュースでも取り上げられてましたよね)
でもその一方で、「人を選ぶゲーム」「途中でやめてしまった」という声もあり、気になっているけど自分に合うのか不安…という人も多いのではないでしょうか。
私も、ストーリー重視のゲームが好きでこの作品を手に取り、66時間プレイしてストーリーをクリアしました。
この記事では、ネタバレなしで、このゲームに感じたことを私なりの視点で正直に書いていきます。
購入を迷っている方の参考になればうれしいです。
『デス・ストランディング2』とはどんなゲームなのか?
『デス・ストランディング2』は『メタルギア』作品で有名な、小島秀夫監督によるアクション・アドベンチャーゲームです。
ジャンルとしては「配送アクション」とでも言うべき、ちょっと変わったスタイルのゲームで、プレイヤーはさまざまな荷物を運びながら、人と人とのつながりを取り戻していくことが目的になります。
世界観と前作との関係
舞台は、謎の現象「デス・ストランディング」によって崩壊した未来のアメリカ。
死者と現世の境界が曖昧になり、世界は分断されています。
プレイヤーは、主人公サム・ポーター・ブリッジズとして、この崩壊した世界を再びつなぎ直すために旅をします。
前作『デス・ストランディング』の直接的な続編となっており、キャラクターや設定も引き継がれています。
ゲームプレイの特徴
このゲームの最大の特徴は「運ぶこと」です。
高低差のある地形や過酷な環境を乗り越えて、荷物を届けていくのが基本プレイになります。
バトル要素もありますが、メインはあくまで「移動」と「つながり」です。
プレイヤーが置いたはしごや橋などは他プレイヤーの世界にも共有され、間接的に助け合えるというオンライン要素も健在。ソロプレイが中心ながら、不思議な一体感を味わえる仕組みになっています。
実際にプレイして感じたこと――70時間のリアルな体験から
ハマれた瞬間はたしかにあった
序盤〜中盤にかけては、配送の中毒性にかなりハマっていました。
メインストーリーとは直接関係のない荷物でも、何度も運ぶことで住人との親密度が上がり、それによって武器の強化や、便利なアイテムの製作が可能になります。
こうしたサブクエストの積み重ねが面白く、毎日コツコツ配送するのが“日課”のようになっていた時期もありました。
でも、途中で「しんどさ」を感じました
ただ、50時間を過ぎた頃から少しずつ飽きがきて、次第にメインストーリーだけを進めるようになっていきました。
ゲームのメインが配送であるとはいえ、道中には敵も出てきます。
しかし、そのバトルがあまり歯ごたえのあるものではなく(ノーマル難易度でプレイしたんですけど、イージーかな?と疑うぐらいバトルは簡単でした)、武器を強化しても戦闘自体の面白さが大きく変わらないのが正直なところでした。
さらに、インフラ整備要素として道路やモノレールを復旧していくシステムもありますが、後半になるにつれて復旧に必要素材の量が膨大になり、手軽に進めることが難しくなってきます。
序盤の達成感がどんどん薄れていき、「もういいかな……」という気持ちになってしまったのが率直な感想です。
ストーリー・演出はどうだったか
映像の見せ方や演出については、さすが小島監督作品だと感じました。
人物の表情や動きのリアルさは本当に映画のようで、「ゲームを見ている」というより「映画を観ている」感覚になる場面も多かったです。
ただ、前作『デス・ストランディング』が発売されたのは2019年。
正直なところ、私は内容をあまり覚えていませんでした。
プレイ前にYouTubeの解説動画で復習はしていたものの、それでもストーリーを完全に理解するのは難しかったです。
ちゃんと内容を理解できた人は、かなりのファンか、直前にやり直している人くらいじゃないでしょうか。。。
話が難解で、感情移入しきれず「全力で感動できた」とは言い切れませんでした。
それでも、プレイ中に何度か「あぁぁ……」としか言えないような、言葉にできない瞬間があったのも確かです。
完全に飲み込めたわけではないけれど、心に引っかかる何かが残る、そんな体験でした。
前作との違い・進化を感じた点
戦闘まわりは、前作よりも明確に強化されていると感じました。
例えば、銃で敵の頭を狙えばヘルメットが外れたり、戦闘時には荷物を一時的に置いて自由に動きやすくなるなど、アクション面のストレスがだいぶ軽減されています。
敵との銃撃戦もしっかり成立していて、「戦えるようになったな」と思える場面が増えました。
また、配達時に使う乗り物も進化していて、より効率的に移動できるようになったのも大きなポイントです。
細かな部分では、快適さや使い勝手が随所で改善されている印象を受けました。
ただ、良くも悪くも「1の正統進化」という印象が強く、どうしても“続編らしさ”以上の驚きは感じにくかったのも事実です。
プレイ中、「あー、これ前作でも見たな」「1のときと同じ感覚だな」と思う場面が何度もありました。
たとえば休憩ルームの演出。トイレやお風呂に入る動作、エナジードリンクを飲む動作など、1つ1つが丁寧に描かれているのは魅力ですが、2でもそれが繰り返され、毎回スキップボタンを何度も押さないといけないのは正直少し面倒に感じました。
全体としてはしっかり進化しているけれど、「2だからこその新鮮さ」よりは、「1の延長線上」にいる感覚の方が強かった、というのが率直な印象です。
前作未プレイでも大丈夫?
正直に言うと、前作をまったく知らない状態でプレイするのは厳しいと思います。
一応、ゲーム内には前作のあらすじをざっくり振り返るムービーが用意されていて、用語の説明もその都度確認できる機能があります。でも、それだけでは理解が追いつかない場面が多いと感じました。
かといって、「じゃあ1から続けてやればいいのか?」というと、それも微妙で…。
というのも、1と2はゲームプレイの基本が「配送」でほぼ同じなので、連続でプレイすると作業感に飽きがきてしまう可能性が高いです。笑
個人的には、「まず1をクリア → 少し間をあけて(半年〜1年後くらい)→ 2をプレイ」くらいの距離感がちょうどいいんじゃないかなと思います。
自分にとって『デススト2』はこういうゲームだった
『デス・ストランディング2』は、確かに唯一無二の体験を提供してくれるゲームでした。
映像や演出のクオリティはとても高く、ゲームというより“映画の中を旅しているような感覚”に何度も浸れました。
配送にも不思議な中毒性があり、序盤は毎日プレイするのが楽しみになるほどハマっていた時期もあります。
でも、後半になるにつれて少しずつ疲れを感じはじめ、ストーリーの難解さや、繰り返しの要素、そして「またこれか」と思ってしまう部分が、楽しさよりも重さとして積み重なってしまいました。
ゲームとしての完成度は高く、前作を遊んだ人であれば確実に進化を感じられる内容です。
ただその反面、「1の延長線上」にある作品でもあるため、前作で感じた作業感やストレスもまた一部残っていました。
私にとって『デススト2』は、「強く印象に残るけど、ずっと夢中で楽しめたわけではない」作品でした。
強く刺さる人には間違いなく忘れられない体験になると思いますが、すべての人にとっての“神ゲー”とは言いきれない、そんな一本です。
このレビューが購入の参考になれば幸いです。